
2025年7月 Writer: Tomoyuki Yamamoto
第53話 世界最大のタコ

ミズダコ=山本智之撮影
■タコは世界に250種以上
高い知性を持つことから「海の賢者」とも呼ばれるタコ。琉球大学の池田譲教授(頭足類学)によると、日本の海には53種のタコ(八腕形目)が生息し、世界全体では250種以上が知られています。

さまざまな種類のタコ。左上から時計回りに「マダコ」(Octopus sinensis)、「サメハダテナガダコ」(Callistoctopus luteus)、「マメダコ」(Octopus parvus)、「スナダコ」(Amphioctopus kagoshimensis)、「ヒョウモンダコ」(Hapalochlaena fasciata)=いずれも山本智之撮影
■腕を広げると3mの「世界最大種」
世界に250種以上いるタコの中で、最も大きくなるのは「ミズダコ」(Enteroctopus dofleini)です。北太平洋の亜寒帯域に分布する巨大種で、腕を広げた大きさは3mにもなります。国内では北海道から東北地方にかけて多くみられ、米国のアラスカ州やカナダなどの沿岸にも生息します。「世界最大のタコ」として『ギネス世界記録』にも掲載されています。

ミズダコ=山本智之撮影
これほど巨大なタコであれば、寿命は数十年くらいありそうに思えます。しかし実際には、ミズダコの寿命は5年ほどと見積もられています。ただ、マダコの寿命が1~2年であることを考えれば、ミズダコは比較的長生きといえるでしょう。
■海中での遭遇、油断は禁物
北海道の知床半島には、ミズダコを観察できるダイビングポイントがあります。私は海中で実際にミズダコに出会い、その大きさに圧倒されました。

ミズダコとダイバー=山本智之撮影
世界最大種のタコだけに、その太い腕で絡み付かれれば、ダイバーにとっては危険です。万が一、強力な吸盤によって、呼吸のためのレギュレーターや水中マスクなどを剥ぎ取られてしまったら、海中でパニックを起こして命取りになりかねません。
ミズダコの側から積極的にダイバーを襲うことはありませんが、海中で巨大な個体に遭遇したときは、油断は禁物です。
■周囲の風景に溶け込む「海の忍者」
成長すると非常に大きくなるミズダコですが、体の色や形を変え、海底の風景に溶け込んでいることがあります。

体を地味な色に変え、海底にひそむミズダコ=山本智之撮影
海底の岩に似た地味な体色になると、実際、あまり目立ちません。また、外套膜(がいとうまく)の表面に小さな突起をたくさん作り、ささくれ立たせることで、体の輪郭を分かりにくくするカムフラージュもできます。ミズダコはこうした変身を瞬時に行うことができる「海の忍者」なのです。
■「ロケット」になって移動する
ミズダコは、泳ぐときにも体の形を変えます。全体をまるでロケットのように細長い形に変え、漏斗(ろうと)から勢いよく海水を噴射。その勢いで一気に移動します。

体を細長くして泳ぐミズダコ=山本智之撮影
■ときには海鳥を襲って食べることも
ミズダコは肉食性です。強い吸着力をもつ吸盤が1本の腕に250~300個あり、この吸盤で甲殻類などのエサ生物を押さえ付けて食べます。腕と腕の間にある「傘膜(さんまく)」という膜で包み込むことで、獲物を逃がしません。

腕と腕の間にある「傘膜」を大きく広げたミズダコ=山本智之撮影
池田さんによると、海外では、ミズダコが野鳥やサメを襲ったという報告もあります。たとえば、カナダのブリティッシュコロンビア州では、ミズダコが海鳥のワシカモメを捕まえ、海中に引きずり込んで食べる姿が観察されています。
■吸盤は「味覚のセンサー」でもある
タコの吸盤は、単に物に吸い付くだけのものではなく、感覚器官でもあります。物の形を識別し、味を認識することができます。吸盤には、触覚や味覚に関わる「受容体細胞」が存在することが、これまでの研究で明らかになっています。

ミズダコの吸盤=山本智之撮影
海中でミズダコを観察していると、その周辺に、小さなオブラートの破片のようなものがフワフワと漂っていることがあります。これは、ミズダコの吸盤の表皮が剥がれ落ちたものです。頻繁に脱皮をして新陳代謝を繰り返しているため、吸盤の表面はいつもツルツルした状態に保たれています。
池田さんは「吸盤には触覚や味覚のセンサーがあるため、常にきれいな状態に保つ必要があるのだろう。こうした仕組みは、強い吸着力を保つ上でも役立っている」といいます。
■主に北海道で漁業の対象に
日本人はタコ好きで知られ、全国で年間2万2848トンのタコが漁獲されています(2023年、海面漁業生産統計調査)。これに加えて、モーリタニアや中国、モロッコなどから計3万1427トンのタコが輸入されています(同年、農林水産物輸出入概況)。
都道府県別でタコの漁獲量が最も多いのは北海道で、全体の約6割を占めます。水揚げの対象になっているのはミズダコ、そして、ミズダコより小ぶりな「ヤナギダコ」(Paroctopus conispadiceus)です。「北海道水産現勢」(同年)によると、北海道のタコの水揚げ量1万4162トンうち、ミズダコは8割にあたる1万1332トン、ヤナギダコは2割の2830トンとなっています。北海道は国内最大のミズダコの産地です。

漁獲されたミズダコ=北海道羅臼町、山本智之撮影
■オスだけが持つ「交接腕」
北海道内の鮮魚店やスーパーでは、ボイルしたミズダコの腕をよく見かけます。腕の先まで吸盤がずらり並んでいることが多いのですが、その中に、腕の先端付近だけツルッとして吸盤がないものがあります。これは、オスだけが持つ特殊な形状の腕で、「交接腕(こうせつわん)」といいます。

ミズダコのオスの「交接腕」=山本智之撮影
ミズダコをはじめとするタコの仲間は、繁殖の際に、オスが精子を「精莢(せいきょう)」というカプセルに詰めてメスへ渡します。このときオスは交接腕を使って、メスの外套膜に精莢を挿入するのです。
ミズダコのオスの場合、8本ある腕のうち「右第3腕」が交接腕です。精子はメスの体内に蓄えられ、産卵時に受精が行われる仕組みです。
■子孫を残し、命を終える
タコの交接腕の先端にある舌状片(ぜつじょうへん)は、種ごとに形状が異なるため、同定を行う際に役立ちます。マダコの舌状片は短い三角形、ヤナギダコはやや長めの円錐形、そして、ミズダコは細長い棒状です。
ミズダコが繁殖して子孫を残せるのは、一生に一度だけ。交接を終えたオスは死んでしまいます。一方、メスはオスよりも数カ月先まで生きることが知られ、産卵後も卵を守り続けます。そして、子どもがふ化するのを見届けると、メスも衰弱してその命を終えます。
■大きな脳を持ち、道具を使用するものも
タコは、無脊椎動物の中では例外的に大きな脳を持っています。そして、「タコは9つの脳を持つ」と言われることもあります。これは、頭部にある脳とは別に、8本の腕の付け根にもそれぞれ「第2の脳」と呼ぶべき部分があり、合計すると9つになるという意味です。ただ、この「第2の脳」について池田さんは「まだ仮説の段階で、解剖学的、あるいは行動学的な研究によって検証する必要がある」と話します。
タコの器用さや賢さを示す事例としては、ガラス瓶のふたを開けて中のエサを食べる行動が挙げられます。また、「メジロダコ」(Amphioctopus marginatus)という種類のタコは、ココナツの殻を持ち歩き、身を隠す道具として使う様子も観察されています。いまのところ、道具を使う行動が知られているのはメジロダコだけです。
■図形の認識もできる
タコが高い知性を持つことは、実験研究によっても証明されています。たとえば、大西洋や地中海に生息する「チチュウカイマダコ」(Octopus vulgaris)は、円や正方形、十字形などの図形を見分けられるといいます。
池田さんの研究室では2013年から、沖縄周辺の海に生息するタコを対象に、学習能力を調べる研究に取り組んでいます。これまでに、「ウデナガカクレダコ」(Abdopus aculeatus)やヒラオリダコ(Callistoctopus aspilosomatis)も図形を認識できることを、実験研究で明らかにしています。
■「最大のタコ」の知能はどのくらい?
ウデナガカクレダコの実験では、コンピューターの画面に映した未知の図形である十字を、いきなり学習するのは難しいことが分かりました。ところが、まず立体の十字などを使って「腕で触れる学習」を行った個体は、コンピューターの画面の十字を図形として認識できることが明らかになりました。池田さんはこの実験結果について「タコは『腕で考える動物』とも言われる。全く新しい物の形を認識する際には、視覚よりも触覚のウエートのほうが大きいようだ」と話します。

ミズダコの頭部=山本智之撮影
暖かい沖縄の海にすむタコを対象に、その知性や感覚世界を探る研究が日々続けられています。
一方、冷たい北の海にすむ「世界最大のタコ」は、はたしてどんな知性を持っているのでしょうか?
池田さんは「ミズダコは人の顔を見分けられるという報告もある。どのくらいの学習能力があるのか、いつか実験して調べてみたい」と話します。
■タコについて深く知る~おすすめの1冊
タコの魅力について、もっと知りたい――。
そんな人へのお勧めの一冊が『タコのはなし―その意外な素顔―』(池田譲著、成山堂書店)です。
タコの生活史や進化、その知性などについて、様々な角度から解説をしています。
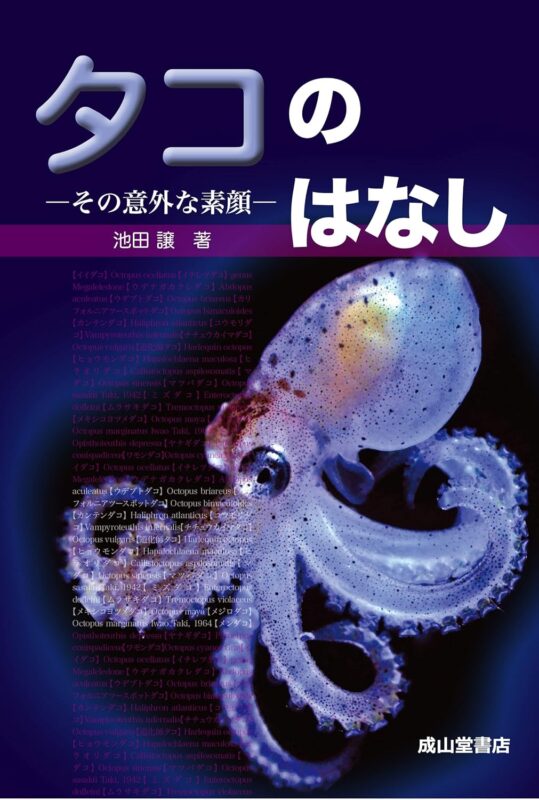
■筆者プロフィール

山本智之(やまもと・ともゆき)
1966年生まれ。科学ジャーナリスト。東京学芸大学大学院修士課程修了。1992年朝日新聞社入社。環境省担当、宇宙、ロボット工学、医療などの取材分野を経験。水産庁の漁業調査船「開洋丸」に乗船し、南極海で潜水取材を実施。南米ガラパゴス諸島のルポを行うなど「海洋」をテーマに取材を続けている。2025年2月には、海上保安庁の巡視船「そうや」の海洋観測に同行した。朝日新聞科学医療部次長、朝日学生新聞社編集委員などを歴任。著書に『温暖化で日本の海に何が起こるのか』(講談社ブルーバックス)、『ふしぎ?なるほど!海の生き物図鑑』(海文堂)ほか。X(ツイッター)は@yamamoto92。
